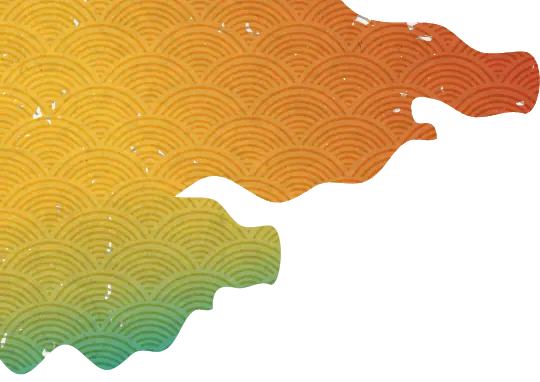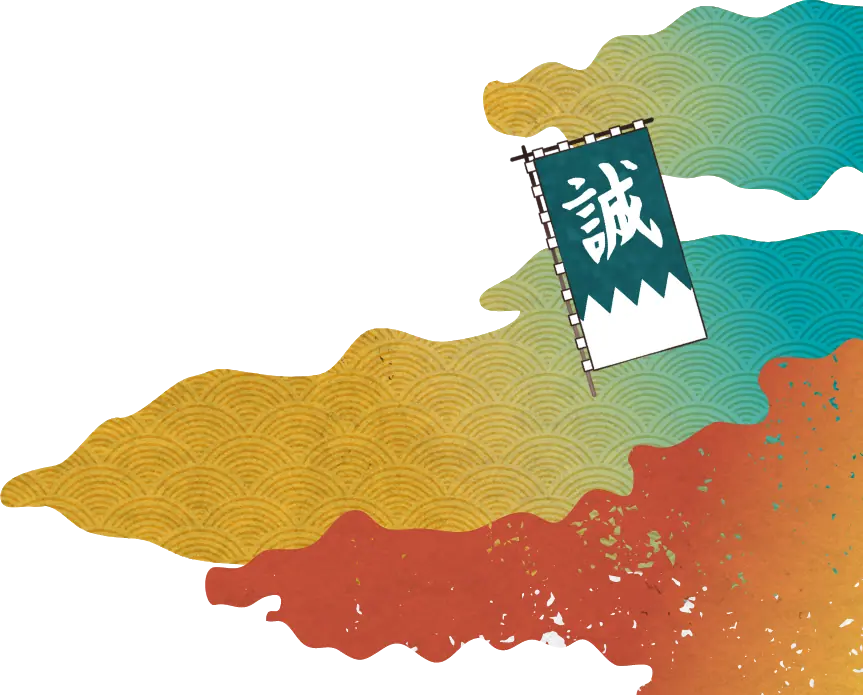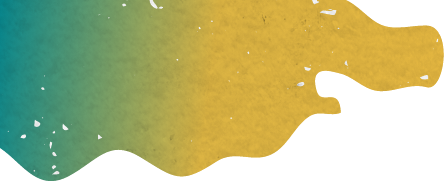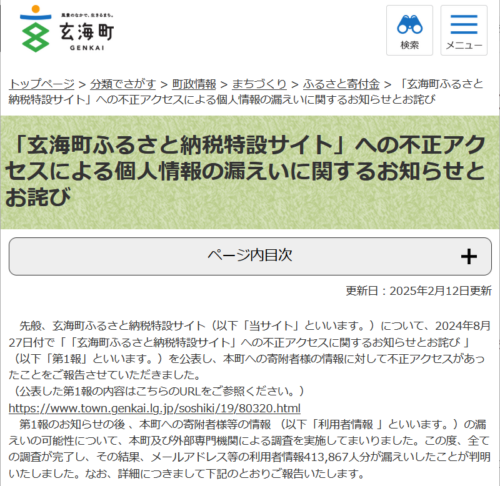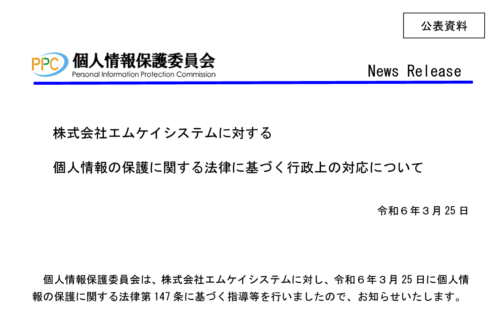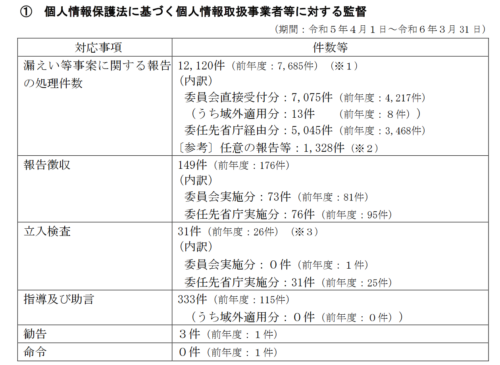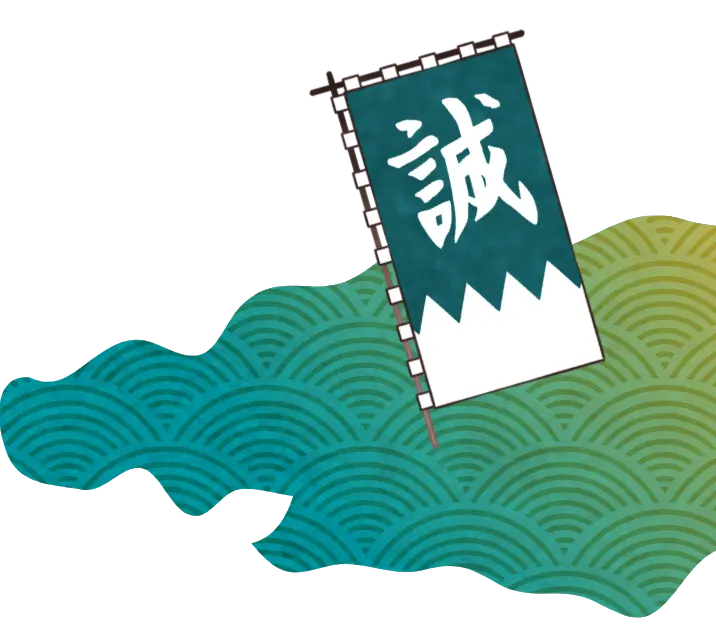皆さんこんにちは。AIプライバシー忍者です。
情報セキュリティや個人情報保護が、企業の信頼を左右する時代。体制が整っていて当然と思われる大手企業で、驚くような個人情報の不適切取扱いが相次いで発覚しました。
今回は、2025年初頭に報じられた2つの重大事案を取り上げます:
●大手損害保険会社4社による他社契約者情報の無断送信
●日本郵政グループにおける預金情報を利用した営業活動
いずれも「大企業なのに、なぜ?」と思うような内容です。本記事では、それぞれの事例を深掘りし、なぜこうしたことが起こるのか?、そして私たちが日々の業務でどう活かすべきか?を解説していきます。
目次
大手損保4社:代理店への出向社員が他社契約者情報を本社に送信
事例の概要
2025年2月、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の4社が、金融庁から業務改善命令を受けました。
発端は、各社の社員が、グループ傘下の乗合型保険代理店に出向していた際に、他社の損保商品を契約した顧客の情報を、本人の同意なく自社の本社に送信していたという行為です。合計すると250万件を超える規模というので、驚かされます。
送信されたのは、顧客の名前や連絡先、契約内容など。自社の商品ではなく他社との契約情報であるにもかかわらず、情報を“持ち帰った”形になっており、個人情報の不正取得・不正利用と見なされました。
金融庁が重視した問題点
- 保険代理店は中立性が求められる場であり、特定の保険会社の利益を優先する行為は、保険業の公正性を損なう
- 出向社員が「表向きは代理店の一員」として働く一方、裏では本社と連携して情報をやりとりしていた
- 顧客本人の同意も説明もないまま、情報が送られていた
結果、金融庁は4社に対して、業務運営の是正、出向制度の見直し、教育体制の強化などを含む厳しい改善命令を出しました。
日本郵政グループ:預金情報をもとに保険勧誘
事例の概要
2025年1月、日本郵政グループの日本郵便株式会社が運営する郵便局で、ゆうちょ銀行の預金情報をもとに、かんぽ生命の保険商品を案内していたことが発覚しました。こちらは1000万人を超える規模と言いますから、度肝が抜かれますね。
具体的には、顧客の預金額が多いことをもとに、保険ニーズが高そうな対象として営業をかけていたというもの。
情報の利用目的が明示されないまま、預金情報を“スコア”として扱うようなセールス活動が行われていたという構図です。
問題の本質は「目的外利用」
金融機関では、顧客の個人情報は「取得目的の範囲内」でのみ利用できるというルールがあります。今回のように、預金取引のために提供された情報を、保険営業のために使うことは、本来の目的を逸脱していると見なされます。
さらに、保険募集に関するルール(保険業法・監督指針)では、顧客にとって適切な勧誘を行う義務(適合性原則)が定められており、資産状況だけをもとにターゲティングする営業手法は問題があるとされる可能性が高いのです。
なぜこんなことが「大企業」で起きたのか?
一見、個人情報保護や法令遵守の体制が整っていそうな大手企業で、なぜこうした問題が起きるのでしょうか?
その背景には、組織構造や文化の複雑さがもたらす“見えにくいリスク”が潜んでいます。
- 組織が大きすぎて「責任の所在」が曖昧に
出向、子会社、グループ会社など、組織の構成が複雑になりすぎて、誰が何をすべきかが見えにくくなる
「本社とやり取りするのは普通」「情報を共有して問題になったことはない」という慣習がルールを上回ってしまう - 現場では「成果重視」が優先される
特に営業部門では、「数字を出せ」というプレッシャーが常にかかる
「情報を使って何が悪い」「ちょっとくらいなら大丈夫」という雰囲気が不適切利用の温床になりうる - コンプライアンス教育やチェック体制の形骸化
研修は受けているが、内容が実務と結びついていない
内部監査も定型的で、実際のリスク行動を検知できていない
このように、形式上のルールは整っていても、実務との乖離や文化的な慣れが、リスクを生み出しているのが現実です。
私たちが学ぶべきことは何か?
今回の2つの事例は、大企業の内部で起きたものであっても、中小企業や一般企業にも十分に起こり得る問題です。
以下のような視点は、どのビジネスパーソンにとっても重要です。
✅ 情報は「なぜ・何のために」取得したかを常に意識する
- 情報は“使えるから使う”のではなく、取得時に示された目的の範囲内でのみ使えるもの
- 別目的で使いたい場合は、本人への説明と同意が必要(ただしそれで十分とは限らない)
✅ グループ内であっても情報共有には明確なルールを
- 「同じグループだからOK」という思い込みがトラブルの元
- 情報の共有先、共有する項目、利用目的などを明文化し、社員に徹底する必要がある
✅ 「迷ったときは立ち止まる」文化づくり
- 「この情報、使っていいのかな?」と感じたら、すぐに上司や法務に確認できる空気があるか?
- 問題が起きた後で動くのではなく、問題が起きないように防ぐ文化を根付かせることが何よりも大事です
おわりに:ルールがあっても、それを“動かす”のは現場の意識
大企業でも起きてしまう個人情報の不適切取扱い。
今回の事例は、組織の大きさや体制の整備だけでは不十分であることを私たちに教えてくれます。
どんなに立派な規程やシステムがあっても、それを使いこなす現場の理解と行動がなければ意味がありません。
日々の業務の中で、以下の3つの問いを習慣にしてみましょう:
- この情報は何のためにあるのか?
- その使い方は、相手にとっても納得できるか?
- この行動は、あとから説明できるか?
その“立ち止まる習慣”が、企業の信頼と、情報を守る力につながっていきます。
🛡️ 参考リンク
金融庁(損害保険会社4社に対する行政処分について)
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250324/20250324.html
日本郵政(日本郵政グループにおける非公開金融情報の適切な取り扱いの確保に向けた取組等について)
https://www.japanpost.jp/pressrelease/jpn/2025/20250318195165.html
以上、AIプライバシー忍者でした。
情報管理と信頼構築は、どんなビジネスにも欠かせない基本スキル。次回も、実務に役立つプライバシー&セキュリティ情報をお届けしていきます!